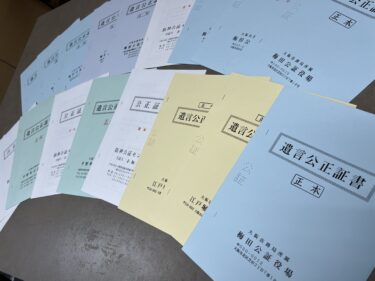「遺言執行者って誰に頼めばいいのだろう。」
「家族や知人など誰にでもお願いできるだろうか。」
もしあなたが遺言書を準備されているのであれば、誰を遺言執行者に選ぶべきか迷うのは当然です。後悔しない選択をするためにも、遺言執行者について知識を身につけておきましょう。この記事では、
- 遺言執行者の役割と責任
- 遺言執行者に向いている人の特徴や選び方
- 選任時に気をつけたいポイント
について、解説していきます。
遺言執行者とは?その役割と重要性
まず、遺言執行者とはどのような存在でしょう。遺言執行者は、遺言者が亡くなった後、財産の分配や名義変更、相続手続きなどを公平かつ確実に進める役割を担います。相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の負担を大きく軽減するためにも、遺言執行者の役割は重要です。
たとえ遺言の内容が明確でわかりやすいものであっても、手続きには専門的な知識や調整力が求められる場合が多く、遺言執行者の選定によって相続手続き全体の円滑さが左右されてしまうこともあります。遺言執行の手続きには、不動産の名義変更や預貯金の解約、遺贈の実行など、実務面での責任が伴うため、適切な人選がのちの安心につながります。
遺言執行者の基本的な役割とは
遺言執行者は、遺言に記された内容を確実に実現することがその役割となります。遺産分割や不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、故人の記した遺言書通りに間違いなく手続きを進める重要な責任を担います。遺言執行者がいれば、相続人同士の意見の食い違いによるトラブルも防ぎやすくなるといえるでしょう。遺言執行者は、相続人全員の代理人として行動します。そのため相続人にとっては、相続手続きの負担を大きく軽減できる点が特徴です。特に、遺言の内容が複雑な場合や相続人が多い場合には、遺言執行者の存在は非常に有効なものとなります。
遺言執行者の権限と制限について
遺言執行者には、遺言書の内容を確実に実現するための強い権限が与えられています。たとえば、遺言執行者は銀行口座の解約や不動産の名義変更など、相続手続き全般を単独で進めることができます。その一方で法律による制限も設けられています。たとえば、遺言書に記載されていない内容や、相続人の生活に重大な影響を及ぼす場合には、勝手に判断して行動できません。また、当然のことではありますが、遺言執行者は私利私欲で財産を動かすことはできません。必ず遺言内容と法律に従う義務があります。
遺言執行者を選任するメリットとデメリット
遺言執行者を選任することには、大きなメリットがあります。遺言執行者を選ぶことで、相続人同士の意見対立や遺産分割協議の混乱を避けやすくなることが挙げられます。
しかし、反対にデメリットもあります。選任をすることで発生する手続きや費用、また執行者の選び方によってはトラブルの火種となるケースもあるため、慎重な判断が求められます。執行者が不適任だった場合や、報酬を巡るトラブルが起こる可能性もあります。遺言の内容や相続人の状況に応じて、最適な人選や選任方法を検討することが重要です。例えば、専門家を執行者に指定することで、法律的な手続きがスムーズに進むといえるでしょう。一方、費用負担が大きくなるデメリットもあります。以下にてさらに詳しく説明していきます。
選任するメリットとその効果
遺言執行者を選任する最大のメリットは、遺言内容が確実に実現されやすくなる点です。遺言執行者がいれば、遺言書に書かれた財産分けや手続きがスムーズに進みます。相続人同士のトラブルも避けやすくなります。特に、相続人同士があまり縁のない関係である場合には、遺言執行者の存在が大きな安心につながります。
また、遺言執行者には法律上の権限が与えられるため、銀行や法務局などでの手続きも円滑に行えます。さらに、第三者が間に入ることで公平性が保たれやすいといえます。遺言執行者を選任しておくと、遺言内容の実現、そして相続手続きの円滑化が期待できるといえるでしょう。
選任しない場合のリスクとは
遺言執行者を選任しない場合はどうでしょうか。遺言の内容がスムーズに実現されない可能性が高まります。遺言書が存在しても、記載された内容を実際に手続きする人が決まっていない場合と、誰が手続きをすすめていくのか、また、誰かが手続きを進めた場合でも適正な人が担当しているのか、などといった猜疑心が生まれることも見られるため、相続人同士で迷いや争いが生じることがあるためです。
遺産分割や不動産の名義変更、銀行口座の解約などは、相続人全員の同意や協力が必要となり、もしいったん関係がこじれてしまった場合、手続きが延々と長引いてしまうといった例も頻繁に見受けられます。最悪の場合には、遺言の内容に不満がある相続人が手続きを妨害するといったケースもあります。このようなトラブルや遺産分割の遅れは、精神的な負担や金銭的な損失に直結してしまいます。
遺言執行者の選び方と具体的な方法
遺言執行者に誰を選ぶか、これは遺言内容を確実に実現するために非常に重要です。誰を選ぶかによって、相続手続きの円滑さやトラブルの有無が大きく左右されます。
選任方法としては、以下の方法があります。
・被相続人自身が遺言書で指定する方法
・指定がない場合に家庭裁判所へ選任を申し立てる方法
例えば、信頼できる家族や親族を指定するケースもあれば、専門的な知識が必要な場合には弁護士や司法書士など第三者を選ぶこともできます。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、状況や遺言内容に応じて最適な選び方を検討しましょう。以下で詳しく解説していきます。
被相続人が指定する方法
遺言執行のために最も確実で意図が反映されやすい方法は、遺言執行者を被相続人が自ら指定することです。遺言書の中で「誰を遺言執行者にするか」を明記することで、相続手続きが円滑に進む可能性が高まります。遺言書には、フルネームや続柄などを正確に記載しましょう。被相続人が自ら遺言執行者を指名することで、相続に関する意思が明確に伝わり、実現しやすくなるといえます。
もし指定がない場合は、家庭裁判所で選任手続きが必要となりますが、時間や手間がかかることも少なくないといえます。 参照:遺言執行者の選任 裁判所ホームページ
家庭裁判所に選任を依頼する方法
遺言書に執行者の指定がなかった場合や、指定された人が辞退した場合には、家庭裁判所に申し立てることで第三者を遺言執行者として正式に選んでもらえます。申し立ては、通常は相続人ですが、利害関係者の場合によっても行うことできる場合があります。
手続きの流れとしては、必要書類を揃え、家庭裁判所に提出します。書類としては、遺言書の写し、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが含まれます。手続きを行った後、遺言信仰者の選任の結果は、裁判所から通知されます。
遺言執行者に適した人材とは?
遺言執行者に適した人材とは、どのような人でしょう。信頼性と誠実さを兼ね備え、法律や手続きに理解がある人物が適任であるといえます。遺言の内容を正確に実現するためには、相続人同士の利害調整や複雑な手続きを冷静に進められる力が求められます。例えば、家族の中で中立的な立場を保てる人や、法律事務所・司法書士・弁護士などの専門家を選ぶケースもみられます。遺言執行者の選任について、以下で詳しく解説していたします。
遺言執行者に向いている人物像
遺言執行者に向いている人。これは、信頼できる誠実な人格を持ち合わせ、事務処理能力や調整力を有する人です。遺言執行者は遺言書の内容を正しく実現するために、財産の管理や分配、各種手続きなど様々な手続きを行う必要があるからです。また、法律や税金の知識があるとさらに安心できます。できれば、感情に左右されやすい方や多忙な方は避けたほうがよいでしょう。遺言執行の手続きは、予想した以上に時間を要する可能性があるからです。
専門家に依頼する場合のメリット
専門家に遺言執行者を依頼するのも良い方法です。最大のメリットとしては、手続きが確実に進むことです。そして、第三者であるからこそ円滑に手続きを行えます。法律や税金、不動産の名義変更などの知識を持ち合わせている専門家は、複雑な作業が含まれる遺言執行に有効です。そのため、遺言執行者として、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをぜひおすすめいたします。相続人間のトラブルを未然に防ぐ調整役としても期待できますし、専門家に依頼すれば、遺言の実現に向けておそらく最短でスムーズな対応が期待できるといえるでしょう。
遺言執行者の報酬と支払い方法
遺言執行者を選任した場合、その報酬や支払い方法についてはどうでしょう。通常、遺言執行者は遺言内容の実現に向けて多くの時間を費やし、また責任も担うため、無報酬というわけにはいかない場合が多いです。そのため、適切な報酬設定や支払いのタイミングについても想定しておきましょう。

報酬の相場と支払いのタイミング
遺言執行者の報酬は、一般的に遺産の総額や業務の内容によって異なります。一般的な相場としては、遺産総額の1~3%程度が目安とされています。
たとえば、遺産が3,000万円の場合、報酬は30万円から90万円ほどになることが多いです。報酬の支払い時期は、一般的に、遺言執行者がすべての業務を終えた後、つまり遺産分割や名義変更などが完了したタイミングとなることが多いです。金額が高額であるという印象を受けられる方もいらっしゃるかと思いますが、業務の煩雑さや責任の重さを考えると、適正な金額とも言えます。遺言書に具体的な報酬額が記載されている場合は、その金額が優先されます。報酬の支払い方法は、現金や預金から直接支払うケースが多いです
報酬を負担するのは誰か?
遺言執行者の報酬は、基本的に相続財産から支払われることが一般的です。つまり、遺言執行者が遺言の内容を実現するために働いた対価は、相続人全員が受け取る財産の中から公平に分担される仕組みとなっています。もし遺言書に、遺言執行者の報酬金額が具体的に書かれている場合は、その金額に従って支払われます。
一方、遺言書に報酬の記載がない場合は、相続人と遺言執行者との間の話し合いで決める、もしくは家庭裁判所が適切な額を判断します。原則として、遺言執行者の報酬は全相続人が均等に負担するため、特定の人にだけ負担が集中することはありません。
遺言執行者の解任と辞任の手続き
通常はあまり見られないことであると思われますが、遺言執行者の解任や辞任の可能性も考えられます。たとえば、遺言執行者が不適切な行為をした場合や、健康上の理由などで職務が困難になった場合、改二にゃ辞任手続きが発生する可能性があります。適切に手続きを行うことで、相続人や関係者の不利益を防ぐことができます。
遺言執行者の役割は財産分配や遺言内容の実現に直結するため、信頼できない執行者がそのまま続けると、さらに相続人間での紛争や財産の不正流用などのリスクに発展する可能性も無視できません。
解任の理由と方法
遺言執行者の解任は、通常は認められないものとなっていますが、重大な問題が発生した場合に限り認められています。遺言執行者がその職務を適切に果たさない、または不正行為を行った場合に限って、相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで解任が可能です。
たとえば、遺言の内容に反する行為や、相続人との信頼関係が著しく損なわれた場合も解任理由となります。解任の手続き、相続人が好き勝手に行えるわけではなく、家庭裁判所に申し立て書を提出し、裁判所が審理したうえで判断します。解任は例外的なことですので、申し立てには、具体的な証拠や理由の提示が必要です。
辞任する際の手続き
遺言執行者が辞任したいと考えた場合、これも勝手に行うことはできません。家庭裁判所の許可を得る手続きが必要です。遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な役割を担っていますが、やむを得ない事情が生じたときは辞任が認められます。体調を崩して続けられないといった理由で辞任をすることが必要となった場合は、辞任理由を書いた申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。その後、裁判所が事情を審査し、許可が下りれば正式に辞任できます。
遺言執行者に関するよくある質問
遺言執行者を辞退することは可能か?
結論から言って、遺言執行者は辞退することが可能です。たとえ遺言で指定された場合でも、本人の意思で辞退することができます。そして、辞退の手続きは、原則として家庭裁判所へ辞退の意思を申し出ることで行えます。遺言執行者の役割は財産の分配や名義変更など責任が重いため、体調や家庭事情、仕事の都合などで辞退を希望する場合は、必要に応じて家庭裁判所で正式な手続きを行います。
遺言執行者が複数いる場合の対処法
遺言執行者が複数いる場合は、基本的に遺言書の内容に従って共同で業務を進める必要があります。複数人で担当する場合は、全員の判断が一致しないと手続きが進まないことが多いため、事前の話し合いにて役割分担をしておくことが重要であるといえるでしょう。また、遺言書に代表者や決定権を持つ人を明記しておくと、よりスムーズに手続きをすすめることができます。さらには、家庭裁判所に調整を依頼する方法もあります。
相続人が遺言執行者の業務を妨害したらどうなるか?
上記にて少しお話いたしましたが、相続人が遺言執行者の業務を妨害した場合はどうなるのでしょう。遺言の内容どおりに手続きが進まなくなる恐れがあるため、法律上の対処が必要となります。たとえば取り分を失うことを恐れ、遺産分割や名義変更を拒否する相続人がいた場合も、遺言執行者には法的な権限があり、正当な理由なく妨害された場合は家庭裁判所に「妨害排除の申立て」を行うことができます。この申し立てにより、執行者は裁判所の力を借りて業務を遂行できるようになります。補足としてお伝えすると、あまりにも妨害が悪質な場合は損害賠償請求や刑事責任が問われることもあります。
まとめ:遺言執行者の選び方と役割を理解し安心を手に入れよう
今回は、遺言執行者の選任について
・遺言執行者の基本的な役割や責任
・選任時に注意すべきポイントや失敗しないコツ
・適切な人選や専門家の活用方法
上記のポイントをお伝えいたしました。 関連:自筆証書遺言の書き方と無効になりやすい例を完全攻略!