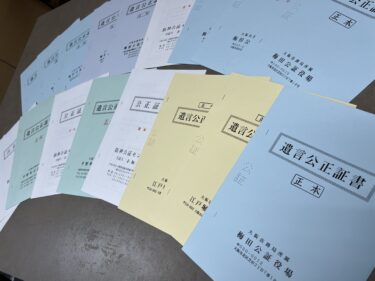「自筆証書遺言ってどのように書けばよいのだろう。」
「せっかく遺言を準備しても、思ったとおりになるのだろうか。」
自筆証書遺言は自分で手軽に作れます。その反面、書き方や決まりごとを守らないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。この記事では、これから自筆証書遺言を作ろうと考えている方に向けて、
・自筆証書遺言の基本的な書き方
・無効になりやすい例や注意点
・有効な遺言書にするためのポイント
以上の内容をまとめています。
自筆証書遺言とは何か?
自筆証書遺言とは?遺言者が自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印することで作成する遺言書の形式です。手軽に作れることから、多くの方が利用していますが、正しい手順を踏まないと無効になるリスクもあります。遺言は、自分の思いを確実に残す有効な手段ですが、法律で定められた要件を満たさないと、せっかく書いた内容が実現されないといった結果も発生するため、正しい認識を持つことが大切です。
自筆証書遺言の利点
なんといっても、自筆証書遺言の最大の利点は、自分一人で手軽に作成できる点です。基本的に費用もかかりません。公証人などの専門家に依頼する必要がないため、思い立ったとき、いますぐにでも書き始めることができます。また、一人で作成をすることができるため、家族など誰にも知られずに準備をすることができます。
自筆証書遺言の欠点
自筆証書遺言には、手軽に作成できる反面、いくつかの欠点も存在します。法律で決められた形式に少しでも不備があると無効になる恐れがあります。
例えば、日付や署名が抜けていたり、誤って記載をした場合の訂正方法を間違ってしまうという例があります。また、自筆証書遺言に記載をした内容が曖昧だと相続人同士で解釈が分かれ、争いの原因になることも少なくありません。さらに、作成したのちの保管場所によっては、本人が亡くなった際にも遺言書がだれにも見つけられないといったおそれや、また逆に見つかった場合に改ざんされてしまうという可能性もあります。このような点を理解し、慎重に作成し、適切な場所に保管することが重要です。
法務局での保管の可能性
上記のようなデメリットをふまえて、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。これにより、遺言書の所在が分からないという心配はありませんし、また、改ざんされてしまう恐れを防げます。さらに、法務局での保管を利用すると、相続開始後の「検認」という家庭裁判所での手続きが不要となります。自筆証書遺言の保管手続きは本人が直接法務局に出向き、必要書類と共に遺言書を提出することで完了します。
さらなるメリットとして、保管の申請時には、遺言書が法律上の形式を満たしているか最低限の確認が行われるため、形式ミスによる無効リスクも減少すると言えるでしょう。参照:自筆証書遺言保管制度 法務省
自筆証書遺言の正しい書き方
全文を自筆で記載する
自筆証書遺言を書く際は、いつくかの条件があります。ひとつ目として、遺言の全文を必ず自分自身の手で書くことが必要です。パソコンで作成した文章、もしくは本人以外が代筆したものは認められません。自筆であることが条件である理由としては、遺言全文について、本人がその内容を理解し、意思をもって作成したことを示すためです。ちなみに、「字がきれいでないから自筆は困る。」と心配委になる方もいらっしゃるでしょうが、読み取れる程度であれば問題ありません。
用紙や筆記具に特別な決まりはありませんが、消えやすい鉛筆や消せるボールペンは避けましょう。仮に、遺言の一部が消えていて読めないというようなことが起こった場合、残された家族間で「本当に本人が書いたものなのか」と疑問を生じさせる要因にもなってしまいます。

署名と捺印の重要性
署名と捺印、これは自筆証書遺言を作成する際に極めて重要です。これらは本人の意思で作成されたことを証明する決定的な要素となります。署名は、遺言書本文と同じく必ず遺言者本人が自分の手で書かなければいけません。印鑑については実印・認印どちらでも構いませんが、銀行印や普段使っている印鑑を使う方が後のトラブルを避けやすいといえるでしょう。押印がない場合や他人が署名した場合は、遺言自体が無効となってしまう可能性があるため注意が必要です。
正確な日付の記入
正確な日付。これも、自筆証書遺言を書く際に絶対に欠かせません。日付があいまいだったり抜けていたりすると、その遺言自体が無効と判断されることがあります。「2025年9月4日」といったような日付はもちろん有効であるといえます。日付の有効性を問われる例をあげてみます。
・有効である日付:2020年東京オリンピック開幕日
・無効である日付:2025年吉日
「東京オリンピック開幕日」は、一見あいまいな日付に見えますが、確認をすれば具体的な日付が特定できます。一方の「2025年吉日」については、日付の特定ができません。法律では「年月日」を明記することが厳格に求められていますが、日付がはっきりしていないと、複数の遺言が存在した場合にどちらが有効か判断できなるため、あいまいな日付では無効と判断されます。複数の遺言が存在した場合、あいまいな日付の記載であると、どちらの遺言が有効であるのかわからず、相続人同士の争いにつながる恐れもあります。よって遺言作成の際には、必ず「令和7年9月4日」など、数字で正確に記入しましょう。
訂正時のルールを守る
自筆証書遺言を作成している際に書き損じをしてしまった場合にもルールがあります。記載した内容を訂正する際は、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正内容を余白に明記し、さらにその近くに署名と印を押すことが求められています。消しゴムで消す、修正液、修正テープを使用するというような方法をとると、のちに誰が訂正したのかわからないという疑いが生まれ、遺言自体が無効になる恐れが高まります。訂正時は必ず「二重線・訂正内容の記載・署名と捺印」の3点を守ることが重要です。
参照:「吹田で遺言作成を安心サポート|初心者向け手続きと注意点ガイド」
遺言内容を具体的にするためのポイント
財産を明確に把握する
自筆証書遺言を書く際には、まず自分が所有する財産を正確に把握することが重要です。財産の内容があいまいだと、遺言の内容が実行できなくなったり、相続人同士で無用な争いが生じる可能性が生まれます。財産には現金や預貯金だけでなく、不動産、自動車、株式、貴金属、骨董品など多様なものが含まれます。財産についてより詳細に、たとえば不動産であれば登記簿謄本に記載された所在地や地番、金融資産なら銀行名や口座番号まで記載するとよいでしょう。
財産の全体像を具体的に把握し、詳細に書き出すことが遺言作成の第一歩となります。
相続人と財産配分の明示
自筆証書遺言では、誰にどの財産を渡すのかを明確に記載することも重要です。遺言書から相続人や財産の指定を読み取ることができない場合、残された家族などが財産の分け方について悩んでしまう原因にもなります。また、内容があいまいであると、遺言自体が無効となる恐れもあります。
「大阪府吹田市〇〇町の土地(地番〇〇番)を長女〇〇に相続させる」といったような明確な方法で、財産の内容と相続人の氏名を記載しましょう。もし複数の相続人がいる場合は、それぞれの配分割合も明示しておくことをおすすめします。
遺言執行者の指定
自筆証書遺言を作成する際、遺言執行者の指定を行うことも非常に有効な方法です。遺言執行者を明記しておけば、相続手続きがスムーズに進み、遺言内容の実現性が高まります。遺言執行者は財産の分配や名義変更など、遺言の内容を具体的に実行する役割を担ってくれます。遺言作成者が信頼できると思う人、もしくは専門家を指名しておくことにより、相続人同士のトラブルも予防できるといえるでしょう。遺言執行者の氏名や住所を遺言書に明記し、実際にその人が引き受ける意志があるか事前に確認しておくことが大切です。
遺言執行者を指定しない場合は、相続人の中から選任する必要があります。選任についても手続きが複雑化しやすい傾向にあるため、注意が必要です。
自筆証書遺言が無効になるケース
共同遺言の無効性
自筆証書遺言が無効になってしまう例をご説明します。絶対に避けなければならないのが、共同遺言です。共同遺言とは、一通の遺言書に連盟で遺言を記載することを言います。たとえば、夫婦や親子など複数人が一通の遺言書に記すといった例があたります。日本の法律では自筆証書遺言は必ず一人で作成しなければならず、共同で作成した遺言は無効となります。夫婦で一緒に遺言書を作成したいという意向は想像できなくはないですが、実際には法的効力が認められないものとなるため避けるようにしてください。自筆証書遺言の際には、遺言者それぞれが自分の意思を自筆で記し、署名と日付、押印を必ず行う必要があります。
遺留分侵害のリスク
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる財産の割合のことを指します。たとえば、子や配偶者がいる場合、これらの人には必ず一定の財産が保障されています。遺留分を無視した内容にすると、後で遺留分を請求されトラブルになる可能性があります。自筆証書遺言を書く際は、遺留分の範囲を事前に確認し、相続人全員の権利を侵害しない内容にすることが大切でしょう。遺留分を考慮することで、遺言が無効になってしまうというリスクを避けることができます。
検認を受けずに開封しない
ご家族の誰かが亡くなり、その後自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での「検認」という手続きを受けずに遺言書を開封してしまうと、重大なトラブルにつながる可能性があります。検認とは、遺言書が本物であることや内容の確認、改ざん防止のために家庭裁判所で行う手続きです。検認前に開封してしまうと、法律上は5万円以下の過料が科されることもあります。また、うっかりと開封してしまったことにより、相続人間での信頼関係が損なわれる原因にもなります。 参照:「遺言書の検認」裁判所ホームページ
万が一開封してしまった場合は、速やかに家庭裁判所に相談することが重要です。遺言書を見つけたら、封をしたまま速やかに家庭裁判所に持参し、正しい手順で検認を受けましょう。
専門家に相談するメリット
無効リスクの回避
自筆証書遺言が無効になるリスクを避けるためには、法律の細かい決まりを認識し、法律にのっとって遺言書を作成することが重要です。そのため、専門家に相談して内容や形式をしっかり確認してもらうことが確実な方法であると言えます。専門家にチェックしてもらうことにより安心感も得られるでしょう。遺言書作成について無料相談を行っている場合もありますので、活用してみてはいかがでしょうか。
遺言執行者に任せる安心感
遺言執行者を指定し、手続を任せることには大きな安心感があります。自筆証書遺言では、遺言執行者を指定しなくても法的には成立しますが、実際には相続手続きや不動産の名義変更など、複雑な作業が発生する場合が多いでしょう。また、遺言執行者を指定しておけば、専門知識を持つ第三者や信頼できる親族が手続きを代行し、遺言の内容を確実に実現してもらえると言えるでしょう。特に、相続人同士の意見が食い違う場面では、遺言執行者が中立的な立場で進行できるため、トラブル防止にもつながりますし、残された家族の心労を減らすこともできます。
自筆証書遺言に関するよくある質問
遺言書と遺言状の違いは?
人によって言葉の使い方が異なり、「遺言書」と呼ぶ方がいたり「遺言状」と言う方もいます。しかし、法的な意味で正しいのは「遺言書」です。正式に効力が認められるのは「遺言書」であり、「遺言状」という表現は一般的な呼び方であると言えるでしょう。実際に、家庭裁判所などでも「遺言書」として扱われます。遺言書は、相続や財産分与の場面で重要な役割を持ちますので、法律的にも正しい「遺言書」という表現を使用することをおすすめします。
自筆証書遺言の保管方法
上記でも説明いたしましたが、自筆証書遺言の保管方法について結論から言うと、紛失や改ざんのリスクを避けるため、信頼できる場所に厳重に保管することが重要です。せっかく正しく作成した遺言書でも、見つからなかったり第三者に内容を書き換えられてしまったりすると、その効力が失われてしまいます。具体的な方法としては、自宅の金庫や引き出しにしまう方法、信頼できる家族に託す方法があります。そして何よりも安心であると言えるのが、法務局での遺言書保管制度を利用する方法であると言えます。法務局の制度は、遺言書の存在証明と安全な保管ができる点で安心感が高いでしょう。
まとめ:自筆証書遺言の書き方と無効例で安心を手に入れる
今回は、遺言書の作成を安心して進めたい方に向けて、
・自筆証書遺言の正しい書き方のポイント
・無効になりやすい具体的な例
・トラブルを防ぐための注意点
上記について、解説いたしました。関連:遺言執行者を誰にする?選び方と役割を解説!失敗しない秘訣